イエスは復活された・十字架って何?
- 出演者
- 田村治郎
- 制作
- PBA 太平洋放送協会
- 再生時間
- 5min
- タグ
-
- イースター
もっと詳しく見る
- アップロード日
- 2025.04.22
- カテゴリ
- 人物・人生
- 放送日
- 2025.04.22
「世の光」の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。グレース宣教会牧師、ハンガーゼロ巡回牧師の田村治郎です。
私は若い頃からあまり装飾品、指輪やネックレスなどを身につける習慣はなかったのですが、20歳前後に七宝焼きの綺麗な十字架のネックレスをつけていたことがありました。十字架というと私にとってはアクセサリーの一つで、教会のシンボルであることさえ知りませんでした。しかし、教会に行き始めてその真の意味を知って愕然となったことを覚えています。十字架は、古代アッシリア人の考案とされる極刑の道具でした。目的は征服地の敵兵の処刑でしたが、ただ殺すだけでなく、城門の外にさらして、なるべく長く苦しむようにした惨たらしいものでした。
この十字架刑と同じように、日本にも磔刑、はりつけの刑がありました。東京の品川区にある鈴ヶ森刑場跡は、今もその一画が保存されていて、この鈴ヶ森刑場独特の処刑法であった「火炙りの刑」や「磔の刑」などの、当時の石でできた台座などが残されていて、そこは歌舞伎の演目で知られる「八百屋お七」の火炙りの刑で有名な場所です。刑場付近に共通することは、「泪橋」という地名が多く残っていることです。同じく東京の南千住にある小塚原刑場近くには、その当時「思い川」にかかっていた橋を泪橋と呼んでいました。鈴ヶ森でも、近くの立会川にかかっていた橋も現在は「浜川橋」と名前が変わってしまっていますが、やはり「泪橋」と呼ばれていました。これら「泪橋」は、罪人にとってはこの世との最後の別れの場であり、家族や身内の者には、処刑される者との今生の別れの場、お互いがこの橋の上で泪を流したことから、この名が付けられたと言われています。どの刑場跡に行っても、当時の処刑が「見せしめ」の要素が強くあることに気付きます。
極刑と言われる、あの鈴ヶ森の「磔刑」は、罪人を何時間も苦しませる、その惨たらしい極めて見せしめの要素も強いものでした。このような刑場を巡るたびに、いつも私の思いに浮かぶのはイエス・キリストの十字架刑です。そのイエス・キリストの十字架刑は死ではおわらずに、復活があり、死という絶望を覆す、希望があること。これが十字架の意味であり、教会のシンボルなのです。
私は若い頃からあまり装飾品、指輪やネックレスなどを身につける習慣はなかったのですが、20歳前後に七宝焼きの綺麗な十字架のネックレスをつけていたことがありました。十字架というと私にとってはアクセサリーの一つで、教会のシンボルであることさえ知りませんでした。しかし、教会に行き始めてその真の意味を知って愕然となったことを覚えています。十字架は、古代アッシリア人の考案とされる極刑の道具でした。目的は征服地の敵兵の処刑でしたが、ただ殺すだけでなく、城門の外にさらして、なるべく長く苦しむようにした惨たらしいものでした。
この十字架刑と同じように、日本にも磔刑、はりつけの刑がありました。東京の品川区にある鈴ヶ森刑場跡は、今もその一画が保存されていて、この鈴ヶ森刑場独特の処刑法であった「火炙りの刑」や「磔の刑」などの、当時の石でできた台座などが残されていて、そこは歌舞伎の演目で知られる「八百屋お七」の火炙りの刑で有名な場所です。刑場付近に共通することは、「泪橋」という地名が多く残っていることです。同じく東京の南千住にある小塚原刑場近くには、その当時「思い川」にかかっていた橋を泪橋と呼んでいました。鈴ヶ森でも、近くの立会川にかかっていた橋も現在は「浜川橋」と名前が変わってしまっていますが、やはり「泪橋」と呼ばれていました。これら「泪橋」は、罪人にとってはこの世との最後の別れの場であり、家族や身内の者には、処刑される者との今生の別れの場、お互いがこの橋の上で泪を流したことから、この名が付けられたと言われています。どの刑場跡に行っても、当時の処刑が「見せしめ」の要素が強くあることに気付きます。
極刑と言われる、あの鈴ヶ森の「磔刑」は、罪人を何時間も苦しませる、その惨たらしい極めて見せしめの要素も強いものでした。このような刑場を巡るたびに、いつも私の思いに浮かぶのはイエス・キリストの十字架刑です。そのイエス・キリストの十字架刑は死ではおわらずに、復活があり、死という絶望を覆す、希望があること。これが十字架の意味であり、教会のシンボルなのです。
コメント
番組に対するコメントはまだありません。ぜひ感想をお願いいたします。


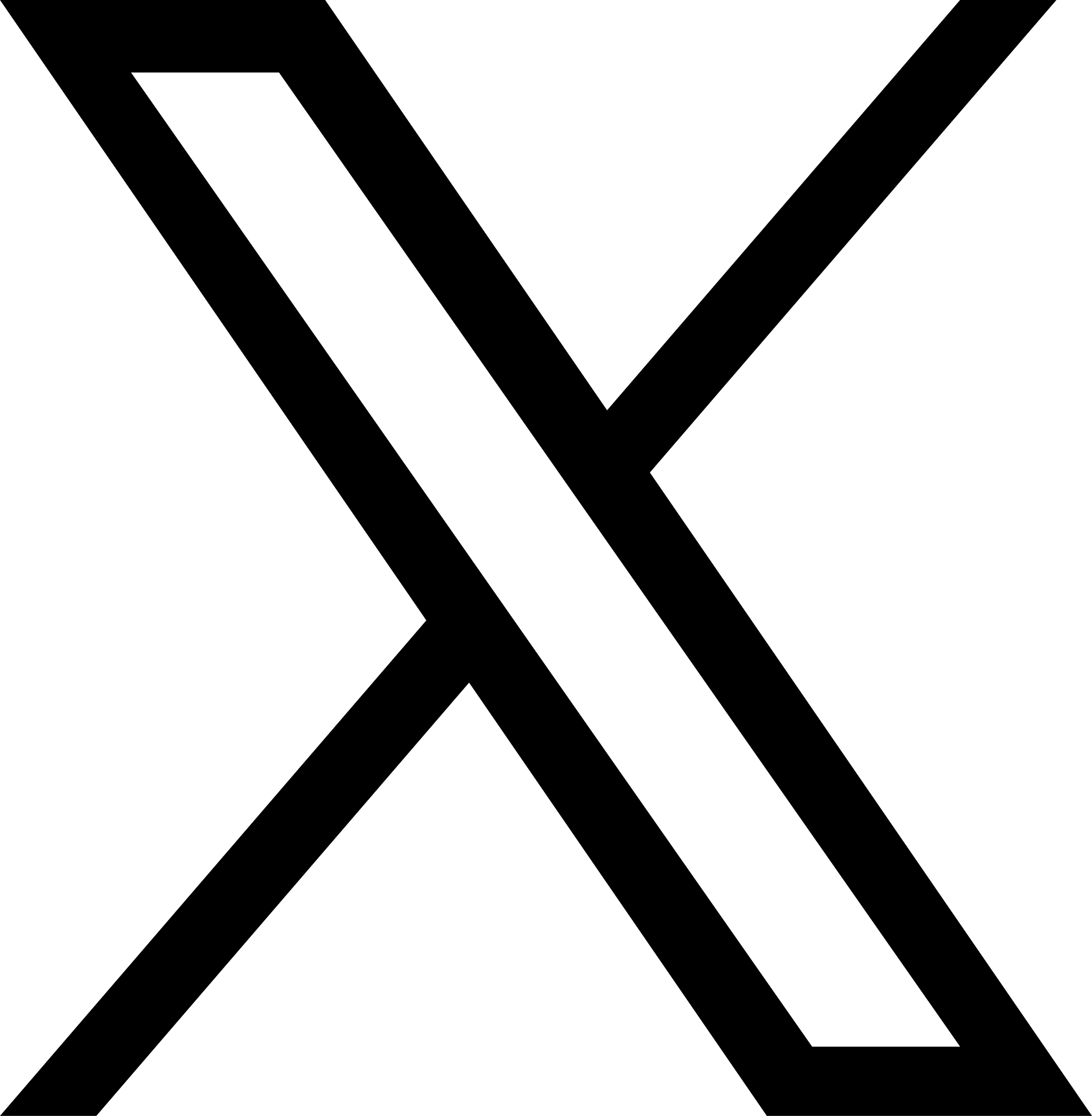
 いいね登録
いいね登録 いいね解除
いいね解除


















